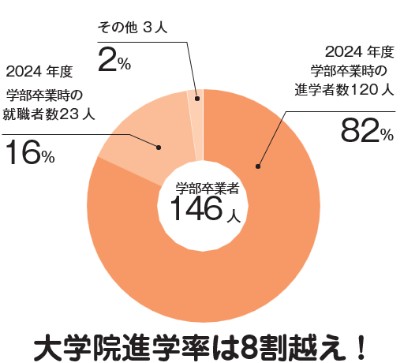情報工学科
Departments
学部・大学院・センター
次世代の新たな情報システムを実現し人にやさしい高度情報化社会を自ら創成する人材を育成します
情報工学科では、人にやさしい次世代の高度情報化社会を自ら創成できる人材を育成します。特に、情報ネットワークなどの基盤となるインフラ技術に加えて、人工知能(AI)やメディア情報処理などの応用技術の習得が欠かせません。本学科は、情報化社会を担う技術者として必要な要素を網羅する、3つの教育プログラムから構成されています。
1)ネットワーク分野

コンピュータやネットワークの新しい技術やサービスを創造するために必要な幅広い分野の基盤技術と基礎知識を学びます。
2)知能情報分野

人を模したAIをつくるために、人が行っていることをコンピュータ上で模倣する方法について学びます。
3)メディア情報分野

画像、映像、音声、音楽、文章などのメディア情報を処理する技術、感覚や感性を解析・生成・評価する手法を学びます。
情報工学科の研究紹介
教員からのメッセージ
学生からのメッセージ
未来イメージ
情報システムを実現

デジタル・トランスフォーメーション
情報通信基盤を整備

高度情報通信技術
機械・システムを制御
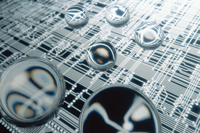
コントロールエリアネットワーク
日常生活を便利・快適に

IoT・ユビキタスコンピューティング
情報機器を設計

情報サービスデザイン
主な就職先
最近の学部の就職先(代表的な10社)
- ㈱ジェイテクト
- 川崎重工業㈱
- 国税庁
- ㈱トヨタシステムズ
- トヨタ車体㈱
- ㈱日本総合研究所
- ㈱ LINE ヤフー
- 名古屋市役所
- UUUM ㈱
- Sky ㈱
最近の大学院の就職先(代表的な20社)
- 愛知県庁
- アイシン㈱
- ㈱ NTT ドコモ
- ㈱サイバーエージェント
- ㈱デンソー
- ㈱日立製作所
- ㈱野村総合研究所
- ㈱村田製作所
- ㈱リクルート
- 西日本電信電話㈱
- 厚生労働省
- ソフトバンク㈱
- トヨタ自動車㈱
- 日本ガイシ㈱
- 日産自動車㈱
- パナソニックホールディングス㈱
- ブラザー工業㈱
- 三菱電機㈱
- ㈱豊田中央研究所
- ㈱豊田自動織機